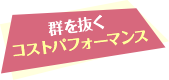Management Column年金制度改正2025~多様な社会と高齢期の安定を支える制度強化へ

令和7年5月に国会へ提出され、6月13日に成立した「年金制度改正法」は、少子高齢化、就労形態の多様化、ジェンダー平等といった社会経済の変化に対応する重要な制度改革です。本改正は、働き方や家族構成の多様性に中立な仕組みを実現しつつ、所得再分配機能の強化、私的年金制度の拡充を通じて、高齢期における生活の安定を目指しています。
本レポートでは、法改正の全体像を4つの柱に分けて整理・解説します。
1.すべての働き手に年金保障を~被用者保険の適用拡大
本改正の柱の一つが、パートタイムや短時間労働者に対する被用者保険(厚生年金・健康保険)の適用拡大です。これまで企業規模や賃金で限定されていた加入条件が見直され、段階的に全労働者に広がっていきます。特に2035年には従業員10人以下の企業にも適用される予定で、就業形態の多様化に対応した年金保障が実現されます。企業への支援策や労働者の保険料軽減措置も用意されており、移行を円滑に進める設計です。
■短時間労働者の加入条件の見直し

- ◆被保険者への支援(就業調整を減らすための保険料調整)
- 適用拡大の対象となる比較的小規模な企業で働く短時間労働者に対し、社会保険料による手取り減少の緩和で、就業調整を減らし、被用者保険の持続可能性の向上につなげる観点から、3年間、保険料負担を国の定める割合(下表)に軽減できる特例的・時限的な経過措置を設ける。(事業主が労使折半を超えて一旦負担した保険料相当額を制度的に支援)
- ◆事業主への支援
- 被用者保険の適用に当たり、労働時間の延長や賃上げを通じて労働者の収入を増加させる事業主をキャリアアップ助成金により支援する措置を検討(令和7年度中に実施、1人当たり最大 75万円助成)。

2.高齢期の就労と年金の両立を促進~在職老齢年金制度の見直し
65歳以上の年金受給者が就労する際の年金支給停止基準額が、50万円から62万円に引き上げられます(2026年施行予定)。この変更により、収入を得ながら年金を受け取る高齢者が増え、就労意欲の維持や人手不足対策に寄与します。これまで「働き損」とされていた構造を是正し、高齢者が持つ力を十分に活かせる環境整備が進みます。
■65歳以上の老齢厚生年金の支給停止の状況

3.男女格差の是正と子育て支援~遺族年金の構造改革
遺族年金制度も大幅に見直され、これまで女性に偏っていた受給構造が是正されます。男性配偶者も対象に含まれ、若年層には原則5年間の給付が設けられました。さらに、子どもに係る遺族基礎年金の受給制限も緩和され、子どもの生活保障が重視されます。また、子を扶養する年金受給者には加算措置が強化されるなど、家庭の形に応じた柔軟な制度が導入されました。

4.基礎年金の水準確保へ~マクロ経済スライド調整の同時終了措置
本改正では、将来的な基礎年金の給付水準低下に備えた重要な方針が盛り込まれました。次期財政検証において、基礎年金と厚生年金の「調整期間」の見通しに大きな差が生じた場合、政府は両制度に適用されるマクロ経済スライドの調整を同時に終了する法制上の措置を講じるとしています。これは、所得再分配機能の低下によって基礎年金のみが削減され続ける不公平を避け、制度全体の持続可能性と公平性を両立させる狙いです。また、その結果として将来の年金総額が現行よりも下回る恐れがある場合には、影響を緩和する追加措置も講じられる予定です。これにより、基礎年金受給者の生活の底支えを図りつつ、制度の信頼性と安定性が高められます。
5.長く働き、より備える~私的年金制度と高所得層の改革
老後資産の形成支援として、個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入年齢上限が「60歳未満」から「70歳未満」へと拡大されました。これにより、国民年金の任意加入者や企業年金未加入者を含め、60代でも継続的な資産形成が可能になります。また、企業年金の運用情報が厚生労働省により開示され、加入者や企業が他社との比較・評価を通じて制度運営を改善しやすくなる「見える化」が図られます。
さらに、厚生年金における標準報酬月額の上限は、現在の65万円から段階的に75万円まで引き上げられる予定です(2027年〜2029年にかけて実施)。これにより、高所得者の保険料負担が実収入に見合った水準となり、その分将来の年金給付額も増加します。この改正は、制度内の公平性を高めるとともに、年金財政の安定にも寄与する重要な施策です。

6.制度の実効性と公平性を高める~周辺制度の見直しと運用の継続措置
今回の改正では、主な年金給付に加えて、社会環境の変化に即した制度の整備も行われています。まず、子のいる年金受給者の生活支援強化として、子に係る加算額の引上げが実施され、加えて老齢厚生年金における配偶者加給年金額についても見直しが行われます。これにより、子育てや家族扶養にかかる支出に対する給付の充実が図られます。
また、外国人労働者の年金制度との関わりについても整備されました。再入国許可を得て一時出国した外国人が、その許可期間内に脱退一時金を請求できないよう見直され、将来的な年金受給への接続性が保たれることになります。
さらに、令和2年改正時から継続されているマクロ経済スライドによる給付調整(報酬比例部分)については、社会経済情勢を見極める必要があるとして、次期財政検証の翌年度(令和12年度)までの継続が決定。制度の持続可能性を担保しながら、柔軟な見直しが可能となるよう配慮がなされています。
■参考資料
年金制度改正法が成立しました【厚生労働省】