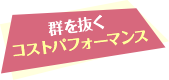Management Columnデジタル人材育成:これから求められるスキルと政策

近年、あらゆる分野でデジタル化・DX(デジタルトランスフォーメーション)の波が急速に広がっており、AI、クラウド、IoTといった技術の進展は、単なる業務効率化の手段にとどまらず、新しいビジネスモデルや価値創造の基盤となりつつあります。会計事務所でもクラウド会計ソフト、AIによる帳簿チェックや自動仕訳、電子申告・電子帳簿保存法の義務化など、業務プロセスの効率化が進んでいます。
しかし、最新のシステムやサービスを導入しただけでは、DXは実現できません。重要なのは、それを活用し、経営課題の解決や新しい付加価値の創出につなげられる“人材”の存在です。デジタル人材は、単にプログラミングやシステム知識を持つ人に限らず、データを読み解き、新たな価値を提供し、組織を巻き込む力を備えた人材を意味します。
しかし経済産業省の調査では、日本企業のデジタル人材の不足を課題として挙げています。多くの企業が「DXの必要性は理解しているが、進められない」現状です。理由として知識やスキルがある人がいないなどの「人材不足」を指摘しています。そのため、裏を返せばデジタル人材を育成・確保できる企業が、市場の変化に柔軟に対応し、持続的成長を実現できる可能性があります。

1.スキルベースの人材育成に向けた政策
政府は「デジタル田園都市国家構想」の中で、2022年度から2026年度の5年間で230万人のデジタル人材を育成するという大きな目標を掲げています。この取組は、単に技術者を増やすだけではなく、社会全体でデジタル活用を当たり前にし、あらゆる産業・地域にDXを浸透させることを狙いとしています。この目標を実現することで、日本全体が「学び続ける社会」へと変わることが期待されています。
- ■デジタルスキル標準による学びの指針
- デジタルスキル標準(DSS)は、経済産業省と独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が策定した、DXの実現に向けた指針です。個人の学習や企業の人材確保・育成に活用することを目的としており、「DXリテラシー標準(DSS-L)」と「DX推進スキル標準(DSS-P)」の2つの標準で構成されています。
- ■学習機会の拡充とアクセスの容易化
- 政府とIPAが運営するポータルサイト「マナビDX」では、民間企業の教育講座をスキル標準に紐づけて一元的に提供。2025年時点で700以上の講座が掲載され、社会人や学生が自分に合ったリスキリングの機会を選べる環境が整いつつあります。
- ■能力保証とキャリア連動
- 情報処理技術者試験をはじめとした国家資格や民間資格を通じて、学習成果を客観的に評価・証明します。資格や認定をキャリアアップや処遇改善と結びつけることで、個人の学びへのインセンティブを強化します。
- ■官民連携によるエコシステム形成
- 人材育成を公的部門が担うだけでなく、学習サービスの提供や現場での実践教育は民間が主導とする役割分担を進めています。これにより、社会全体で学び直しを促進する「リスキリングのエコシステム」を形成し、地域や企業規模を問わず人材育成の裾野を広げることが可能になります。


2.育成の課題とその乗り越え方
デジタル人材の育成には、時間不足や学習意欲の低下、知識の陳腐化、現場への適用難などの課題があります。これを克服するには、「個人の学びの動機づけ」と「企業側の評価・処遇の仕組み」の個人と企業を両方強化することが、育成を加速させるカギとなるでしょう。
| 課題 | 対策のヒント |
|---|---|
| ■時間・リソースの制約 →業務で忙しいスタッフは、勉強時間を確保しにくい
|
企業側は学びを小さなタスクに分割し、短時間でも継続できる仕組みを設ける(例:1日30分、週2回)。さらに「マナビDX」などオンライン教材を活用し、スキマ時間学習を推奨する。 |
| ■モチベーションの維持 →何をどこまで学べばいいか分からず挫折しがち
|
デジタルスキル標準(DSS)の役割モデルを活用し、明確な学習ゴールを設定。成果を可視化し、バッジや修了証など「見える評価」を導入することで小さな成功体験を積ませる。必要に応じて昇進・評価制度と連動させる。 |
| ■知識の古さ・変化の速さ →技術や法制度の変化についていけない
|
IPAや経産省が随時改訂するDSSや試験制度の情報を社内にフィードバックする仕組みを構築。外部研修やセミナー参加を助成金制度(教育訓練給付・人材開発支援助成金)と組み合わせ、継続的にアップデートする。 |
| ■現場への適用ギャップ →学んだ内容を具体業務に落とし込めない
|
ケーススタディ教育(マナビDX Quest等)を導入し、「学び → 実践 → 改善」のサイクルを回す。さらに小規模なDX案件(自動化、データ可視化など)を現場で担当させ、実務で活かす体験を積ませる。 |
| ■学習成果の評価が不透明 →学んだことが正しく評価されず定着しない
|
スキル情報基盤(スキルデータベース)を活用し、取得スキルや資格をデジタルクレデンシャルとして可視化。これにより人事評価やキャリアパスに連動させやすくなり、学習成果が正当に評価される環境を整えられる。 |
3.今後を見据えて
デジタル時代における企業の発展は、人材育成への投資にかかっているといえます。
会計・税務の世界でも、単なる数字処理だけでなく、データの価値を引き出し、顧問先の意思決定支援や業務効率化に貢献することが求められつつあり、デジタル人材の育成は選択肢ではなく、経営的戦略になることが予想されます。
そのため、「どのようなデジタルスキルを持った人材が必要か」を明確化し、それを育てるプランを立て、外部リソースや制度を積極的に活用することで、単なる業務効率化にとどまらず、顧問先への新たな価値提供や、将来的な事務所全体の競争力強化につながることでしょう。
■参考資料
経済産業省「Society5.0時代のデジタル人材育成に関する検討会」報告書-「スキルベースの人材育成」を目指して」経済産業省「デジタル人材の育成」