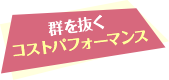Management Column令和7年度地域別最低賃金額改定とそれぞれの見解

令和7年度の地域別最低賃金額改定の目安が、第71回中央最低賃金審議会で取りまとめられました。都道府県の経済実態に応じて全都道府県をABCの3ランクに分類し、Aランクが63円、Bランクが63円、Cランクが64円の引き上げとなりました。そのため、全国の加重平均額が1118円となり、1978年の目安制度開始以来最大となる引き上げが目安となりました。
労働者の生活向上と企業の支払い能力のバランスを図りながら、働く人々の賃金の底上げを目指す最低賃金制度、今回の大幅な引き上げとなったそれぞれの見解を解説します。
1.最低賃金とは
最低賃金制度は、労働者の賃金の最低額を法律で保障する制度です。国が定めた最低賃金額以上の賃金を、使用者は労働者に支払わなければなりません。たとえ労使で合意したとしても、最低賃金を下回る賃金での契約は違法であり、使用者には罰金が課せられます。
最低賃金には「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」の2つあり、「地域別最低賃金」は都道府県ごとに定められ、その地域で働くすべての労働者に適用されます。「特定最低賃金」は、電気機械器具製造業や自動車小売業といった特定の産業で働く労働者にのみ適用されます。
■2025年 最低賃金の目安一覧

2.最低賃金の決定プロセス
最低賃金は、労働者の生活と企業の実態を総合的に判断して決められています。最低賃金の決定プロセスには、中央最低賃金審議会と地方最低賃金審議会という2つの審議会が重要な役割を果たしており、中央最低賃金審議会は厚生労働省に、地方最低賃金審議会は各都道府県労働局に設置されています。
最低賃金の決定や改定にあたっては、以下の3つの要素を考慮します。
- ①「労働者の生計費」
- ②「労働者の賃金」
- ③「通常の事業の賃金支払能力」
特に労働者の生計費を検討する際は、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を送れるよう、生活保護制度との整合性にも配慮がなされます。
審議会では、賃金の実態調査結果をはじめとする各種統計資料を元に分析・検討します。そして、各地方最低賃金審議会での審議を経て、最終的に都道府県労働局長が地域別最低賃金を決定または改定する仕組みとなっています。
3.それぞれの見解:労働者側
中央最低賃金審議会における労働者側の主張は、大きく6つのポイントに集約されます。
第一に、今年の春季生活闘争では昨年の5%台をさらに上回る賃上げが実現したことを指摘。この成果を、労働組合のない職場で働く労働者にも波及させるため、最低賃金の大幅引き上げが必要だと訴えました。
第二に、全都道府県での時給1,000円超えの実現を求めました。さらに中期的な目標として「一般労働者の賃金中央値の6割」を掲げ、継続的な引き上げの必要性を主張しています。
第三に、現状の最低賃金では最低生計費を賄えていないと指摘。特に消費者物価指数が4%強の高水準で推移する中、最低賃金近傍で働く労働者の生活は一層厳しさを増していると強調しました。
第四に、地域間の最低賃金格差の問題に言及。特にB・Cランクの地域で目安を大幅に超える引き上げが相次いだことを挙げ、より建設的な議論を促すため、昨年の実績を踏まえた目安の提示を求めました。
第五に、最低賃金引き上げの雇用への影響は限定的との見方を示しました。むしろ最低賃金の引き上げに伴い労働力人口は増加傾向にあると指摘しています。
第六に、企業の経常利益は堅調に推移しており、賃金支払能力に問題はないとの認識を示しました。その上で、中小・零細事業所での賃上げ実現に向けた政府支援策の拡充を求めています。
以上の主張を踏まえ、労働者側は「誰もが時給1,000円」の実現と地域間格差の是正につながる目安の提示を要求しましたが、最終的な公益委員見解には不満を表明する結果となりました。
4.それぞれの見解:使用者側
中央最低賃金審議会における使用者側の主張は、最低賃金引き上げの必要性を認識しつつも、慎重な姿勢を示しました。
第一に、中小企業の経営環境に関する懸念を表明しました。原材料費や労務費の上昇分を価格に転嫁できていない企業が多く、特に地方の小規模事業者の経営状況は厳しいと指摘。価格転嫁が十分でない状況での過度な最低賃金引き上げは、企業経営を圧迫する恐れがあると主張しました。
第二に、最低賃金決定の三要素(生計費・賃金・通常の事業の賃金支払能力)のうち、「賃金支払能力」を重視する立場を明確にしました。特に賃金改定状況調査の賃金上昇率を重要視し、データに基づいた納得性の高い目安額を求めました。
第三に、最低賃金の地域間競争に対する懸念を示しました。近年、地方最低賃金審議会で目安額以上の引き上げを行う地域が増加しており、隣接地域との競争や最下位回避を意識した判断が見られることを問題視。本来の目的である「セーフティーネット」の役割から外れていると指摘しました。
第四に、最低賃金の発効日について柔軟な対応を求めました。近年の大幅な引き上げにより、企業側の準備期間確保が必要となっています。また、「年収の壁」による就業調整で人手不足が深刻化する懸念もあり、地域の実情に応じた発効日の設定を要望しました。
結果として、使用者側は最終的な公益委員見解に対して不満を表明する形となりました。
5.それぞれの見解:公益委員見解
中央最低賃金審議会の公益委員見解は、最低賃金の引き上げと中小企業支援の両立を目指す立場を示しています。審議にあたっては、令和5年全員協議会での合意事項である「最低賃金法の3要素に基づく丁寧な議論」を重視。「新しい資本主義のグランドデザイン」や「経済財政運営と改革の基本方針2025」も踏まえながら、各種指標を総合的に検討しました。
公益委員は特に、中小企業・小規模事業者への支援を重要視しています。具体的には、生産性向上支援や価格転嫁対策の強化を求めています。業務改善助成金の拡充や、キャリアアップ助成金等での賃上げ支援の充実を要望。また、官公需対策や取引適正化の徹底、事業承継支援なども含めた総合的な経営基盤強化策を提言しています。
価格転嫁については、下請法改正法の確実な執行を求めています。公正取引委員会の体制強化や、省庁間連携の構築を要望。特に価格転嫁率の低い業種への重点的な対応や、下請Gメン等による監視体制の拡充を提案しています。
さらに、「年収の壁」への対応として支援パッケージの活用促進や、行政の業務委託における最低賃金への配慮なども求めています。このように公益委員見解は、最低賃金引き上げの実効性を確保しつつ、中小企業の経営基盤強化を通じた持続可能な賃上げの実現を目指す内容となっています。
6.政府の目標は全国平均1,500円
政府は、2020年代における全国平均1,500円という意欲的な目標を掲げています。この実現に向けて、賃金引き上げを成長戦略の核と位置づけ、持続的な物価上昇のもとで実質賃金を年1%程度上昇させることを目指しています。
しかし、この目標達成には課題も存在します。特に中小企業・小規模事業者の経営基盤強化が不可欠です。そのため政府は、適切な価格転嫁の促進や生産性向上支援、事業承継・M&Aの後押しなど、総合的な支援策を展開。さらに、GX・DXやスタートアップ支援を通じた「投資立国」の実現や、国民の資産形成を促進する「資産運用立国」への転換も進めています。
今回の過去最大となる最低賃金引き上げは、1,500円という目標に向けた第一歩と言えます。賃金上昇を通じた経済の好循環を生み出し、すべての働く人が将来に希望を持てる社会の実現が期待されています。
■参考資料
内閣府「経済財政運営と改革の基本方針2025~「今日より明日はよくなる」と実感できる社会へ~(令和7年6月13日閣議決定) (PDF形式:1.2MB) 」厚生労働省「令和7年度地域別最低賃金額改定の目安について」