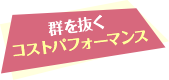Management Column働き方改革と週休3日制

近年、日本の働き方は大きな転換期を迎えています。働き方改革関連法の施行により、残業時間の上限規制や有給休暇の取得義務化など、労働環境の改善が進められてきました。そうした流れの中で、東京都が今年の4月から導入をしたフレックスタイム制を活用した週休3日制は、新しい働き方のモデルケースとして注目を集めています。週休3日制については、業務効率への影響を懸念する声がある一方で、働く人の健康維持やワークライフバランスの向上につながり、結果として生産性の向上やモチベーションアップにつながるという期待の声も高まっています。
1.週休3日制とは
週休3日制は、働き方改革の新たな取り組みとして注目を集める制度です。従来の週休2日制とは異なり、社員が自身のライフスタイルや働き方に合わせて、週に3日の休日を柔軟に設定できる仕組みです。この制度は、育児や介護との両立、自己啓発、余暇の充実など、多様な働き方のニーズに応える施策として期待されています。
- ■週休3日制の形態
- 1:労働時間・給与維持型
- 週の総労働時間と給与水準を維持したまま、1日あたりの労働時間を延長することで週3日の休日を実現します。
- 例えば、1日の労働時間を9~10時間に設定し、4日間で通常の週の労働時間を達成する形式です。この形態を導入する場合、変形労働時間制やフレックスタイム制などの併用が必要となります。
- 2:労働時間・給与削減型
- 週の労働日数を減らすことで、それに応じて労働時間と給与を削減する形態です。1日あたりの労働時間は従来通りに維持しながら、週の総労働時間を減らすことで、より柔軟な時間活用を可能にします。給与は労働時間の削減に応じて調整されます。
- 3:労働時間削減・給与維持型
- 週の労働時間を削減しながらも給与水準を維持する先進的な形態です。1日あたりの労働時間は変更せず、週の総労働時間を削減します。企業側は高い生産性向上が求められ、短時間で成果を上げる策が必要とされます。
週休3日制の導入にあたっては、一斉休業とするか交代制にするか、業務の繁閑期への対応、取引先との調整など、様々な要素を考慮する必要があります。各企業は自社の事業特性や従業員のニーズを踏まえ、最適な形態を選択することが重要です。
- ■選択的週休3日制
- 選択的週休3日制は、従業員が希望に応じて週3日の休日を取得できる柔軟な勤務制度です。週休3日制とは異なり、全従業員一律ではなく、個人の事情や希望に合わせて制度を利用できる点が特徴です。選択的週休3日制は、2021年6月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2021」(骨太の方針)に盛り込まれ、注目を集めています。
2.週休3日制の効果
週休3日制には、働く人と企業の双方にとって大きなメリットがあります。そのため、働く人の生活の質を高めながら、企業の持続的な成長を支援する制度として期待されています。
- ■働く側のメリット
- 多様な働き方を望む人の働き方の選択肢を増やし、ワーク・ライフ・バランスの実現などにつながりやすい。
- ■企業のメリット
- 社員のワーク・ライフ・バランスの実現や人材確保、離職防止、満足度向上、スキルアップなどにつながりやすい。
3.週休3日制 検討・導入のステップ
週休3日制の導入を検討する際は、5つのステップに沿って進める必要があります。これらのステップを着実に進めることで、後々のトラブルを防ぎ、企業と従業員双方にとって効果的な週休3日制の導入が可能になります。なお、導入後も定期的に制度の効果検証と必要な改善を行うことが、制度の定着と成功につながります。
- 【1:導入目的の整理】
- 企業が週休3日制で実現したい事、従業員の働き方ニーズを明確にします。この制度が効果を発揮するには、残業前提の働き方を見直し、休暇を取得しやすい職場風土を醸成することが重要です。自社の現状と課題を整理し、導入目的を明確にします。
- 【2:制度内容の検討】
- 制度形態の選定から始め、具体的な制度設計を行います。
- ・制度形態(「労働時間・給与維持型」、「労働時間・給与削減型」、「労働時間削減・給与維持型」)
- ・対象となる従業員の範囲)
- ・制度利用の条件(事由制限の有無))
- ・休日設定と労働時間)
- ・処遇条件(特に給与削減型の場合))
- ・制度の適用期間)
- ・申請・承認の手続き)
- ・その他の関連制度との調整)
- 【3:運用体制の整備】
- 制度を円滑に運用するための体制づくりを行います。特に週休三日制が選択性で週休2日制の従業員と混在している場合、業務に支障が出ない仕組みの構築が重要です。業務分担の見直しや、チーム全体でのバックアップ体制の確立が必要とされます。
- 【4:法的対応の実施】
-
就業規則の変更や必要な労使協定の締結を行います。特に、変形労働時間制やフレックスタイム制を併用する場合は、それぞれの制度に応じた手続きが必要です。
- ■フレックスタイム制
- あらかじめ定められた総労働時間の範囲内で、従業員が自身の裁量で日々の始業・終業時刻を決めることができる柔軟な勤務制度です。
- フレックスタイム制の導入には、就業規則等で始業・終業時刻を従業員の決定に委ねることを明記し、さらに労使協定で以下の6つの事項を定める必要があります。
- 1:制度の対象となる従業員の範囲
- 2:労働時間を精算する期間(清算期間)
- 3:清算期間における総労働時間
- 4:1日の標準労働時間
- 5:必ず勤務すべき時間帯(コアタイム)※任意設定
- 6:出退勤の選択が可能な時間帯(フレキシブルタイム)※任意設定
- ■1か月単位の変形労働時間制
- 1か月以内の期間で労働時間を柔軟に配分できる制度です。この制度は、特定の日に8時間を超える勤務や、特定の週に40時間を超える勤務が可能になります。ただし、1か月の期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間以内(特例措置対象事業場は44時間以内)となるように設定する必要があります。この制度を導入する際、4点注意が必要です。
- 1:制度の対象となる従業員の範囲
- 2:対象期間と起算日を具体的に定めること(例:毎月1日起算で1か月間)
- 3:労働日と1日ごとの労働時間をシフト表や会社カレンダーであらかじめ明示すること(任意の変更は不可)
- 4:労使協定の有効期間は対象期間より長く設定し、適切な運用のために3年以内程度とすること
-
※特例措置対象事業場とは、常時使用する労働者が10人未満の商業、映画・演劇業(映画製作を除く)、保健衛生業、接客娯楽業の事業場を指します。
- 【5:制度の周知と運用開始】
- 従業員に対して、制度導入の目的や具体的な利用方法、注意点などを丁寧に説明します。
4.今後の週休3日制の動向
日本における週休3日制は、2021年の「経済財政運営と改革の基本方針」で普及促進が示されましたが、2025年7月現在、義務化の予定はありません。政府は企業や個人の自主的な選択を重視する方針を取っており、各企業の状況に応じた柔軟な導入を推進しています。
週休3日制への関心が高まることで、今後は導入企業の成功事例や課題が蓄積され、より実践的な制度設計や運用モデルが確立されていくと予想されます。特に、デジタル化やリモートワークの普及により、柔軟な働き方への需要は一層高まることが見込まれます。
都庁総合ホームページ「令和6年第四回都議会定例会 知事所信表明」
内閣府「経済財政運営と改革の基本方針2021」
厚生労働省「選択的週休3日制の紹介」
厚生労働省「働き方・休み方改革取組事例集(2025年3月発行)」
厚生労働省「フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き」
厚生労働省「1か月単位の変形労働時間制」