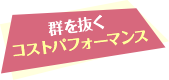Management Column“まだ早い”はもう遅い!事業承継は10年先を見据えて動く時代

帝国データバンクの調査では、「人手不足倒産」が年々増加し、2025年上半期には214件に達し、労働集約型業種を中心に過去最多を更新しています。また、中小企業庁の資料では、「経営者の高齢化が進み、後継者不在、廃業の増加による雇用や技術の喪失が懸念されている」と指摘されています。そのため、事業承継を早期に取り組むことが、経営者の高齢化・後継者不在・技術喪失といったリスクを軽減し、地域経済・雇用を守る観点から極めて重要とされます。

1.事業承継の種類
■親族内承継
経営者の子どもや親族に事業を引き継ぐ形態です。血縁関係があることから、経営理念や企業文化の継承がスムーズで、長期的な視点で準備を進めやすい特徴があります。また、相続や贈与による財産・株式の移転を活用できるため、所有と経営の一体的な承継が実現しやすいメリットがあります。
■従業員承継
役員や従業員など、親族以外の社内人材が事業を引き継ぐ形態です。長年会社で働いてきた従業員であれば、事業への理解が深く、取引先との関係も構築されているため、経営方針の一貫性を保ちやすいメリットがあります。また、経営能力や実績に基づいて後継者を選定できるため、経営の安定性が期待できます。
■M&A(第三者承継)
M&Aとは、親族や従業員に後継者候補がいない場合でも、株式譲渡や事業譲渡を通じて、他の事業者や個人に事業を引き継ぐ方法です。 M&Aの実施件数は年々増加しており、2022年度は事業承継・引継ぎ支援センター経由で1,681件、民間M&A支援機関経由で4,036件が成立しています。また、公的機関による支援体制も整備され、中小企業でも活用しやすい環境が整ってきています。
2.なぜ、早く事業承継に取り組むべきなのか?3つの要因
中小企業にとって事業承継は「経営のバトンタッチ」であると同時に、「会社の未来を守る」ための経営課題です。しかし実際には、多くの経営者が「まだ先でいい」「後継者が決まってから考える」と後回しにしがちです。その結果、承継準備が遅れ、事業の継続が危うくなるケースも少なくありません。
防止策としても事業承継は“早めの着手”こそが最大のリスク対策といえるでしょう。
- ■1:人手不足が「承継の準備」を難しくしている
- 人手不足による倒産件数は過去最多を更新している中、中小企業の多くが採用難・後継者難・熟練者の退職など「人」に関する課題を抱え、承継準備を進めたくても日常業務に追われ、時間が取れない状況にあります。 特に従業員承継やM&Aによる第三者承継では、後継者候補の育成・業務の引継ぎ・取引先調整など、人材面での負荷が大きく、十分な時間と人員が必要です。
- ■2:経営者の高齢化が進み、「待ったなし」の段階の状況
- 中小企業庁の調査では、経営者の平均年齢はすでに60歳を超え、70代で現役を続けている方も増えています。このまま高齢化が進み、経営判断や財務管理の感覚が鈍り、次第に事業の勢いを失うリスクが高まります。また、健康問題や突発的な事情によって「突然の引退」や「急な廃業」を余儀なくされる場合もあります。
- ■3:承継には「長い時間」がかかる
-
事業承継は単なる社長交代ではなく、人・資産・経営権・信用をすべて次世代に引き継ぐプロジェクトです。
後継者の育成だけでも3〜5年、株式・資産の整理や取引先・金融機関との調整を含めると10年単位の準備が必要になることもあります。
例えば、親族承継では相続・贈与の最適化、従業員承継では社内の信頼形成、M&Aでは相手探しやデューデリジェンスなど、いずれも短期間では完了しません。また、承継後の成長(新規事業、デジタル化、人材採用など)まで見据えると、準備開始から完了までを見据えた時間が必要です。
● サプライチェーン事業承継
サプライチェーン事業承継とは、取引先企業の廃業を防ぎ、企業間の繋がりを維持・強化するために行う事業承継の取り組みです。例えば、重要な部品メーカーが廃業すれば、完成品メーカーの生産に支障が出るだけでなく、物流や販売など関連企業にも影響が及び、連鎖的な経営危機を引き起こす恐れがあります。
中小企業の経営者の高齢化や後継者不足が深刻化する中、取引先企業が廃業すると、その影響は直接の取引先だけでなく、地域産業全体に波及する可能性があります。そのため、自社の事業継続のためにも、取引先企業の事業承継状況に目を向けることも重要です。
3.先を見据えた事業承継
事業承継は、単なる社長交代ではなく「会社の未来をつなぐ経営課題」です。
事業承継の構成要素は、大きく「人(経営)の承継」「資産の承継」「知的資産の承継」の3つに分類されます。これらの要素は相互に関連しており、どれか一つが欠けても円滑な事業承継は困難です。特に知的資産は一朝一夕には築けないため、計画的な承継準備が必要となります。
後継者の育成や株式、資産の整理には想像以上に時間がかかります。早期に着手した企業ほど、持続的な成長を実現しています。
逆に、問題を先送りするほど、選択肢が減り、廃業に追い込まれがちです。「まだ早い」ではなく、「今から備える」ことが、企業を次の世代へ確実に残す最善の経営判断と言えるでしょう。
会計事務所としても、経営者の想いと人材のバトンをどう繋ぐかの支援や承継計画を共に考え、地域の企業を未来へ導く役割を果たしていくことが求められているでしょう。
4.事業承継の支援策
全国47都道府県の事業承継・引継ぎ支援センターを中心に、後継者不在の相談からM&Aまでを支援しています。さらに、事業承継・引継ぎ補助金による費用補助、事業承継税制(法人版・個人版)による贈与・相続税の軽減、ファンド・金融支援・法制度特例など、承継準備から実行、承継後の成長までを多面的にサポートする体制が整えられています。
| 事業承継支援 | |
|---|---|
| 事業承継・引継ぎ支援センター | 全国47都道府県に設置された公的相談窓口。 |
| 事業承継・引継ぎ補助金 | 承継、引継ぎを契機とする新たな取組(設備投資・販路拡大等)やM&A時の専門家活用費用、さらに承継や引継ぎ時に発生する廃業、在庫処分等の費用も補助対象。 |
| 法人版・個人版事業承継税制 |
・法人版: 非上場株式を後継者が取得する場合、贈与税、相続税の納税猶予 (特例措置あり)など。 ・個人版: 特定事業用資産の贈与、相続に対し、贈与税、相続税の猶予制度。 |
| 事業承継ファンド | 新事業展開、グループ化、経営基盤強化を目指す中小企業が、ファンドからの資金提供や経営支援を受けられる制度。 |
| 融資・金融支援 (日本政策金融公庫等) |
事業承継・集約化を図る中小企業が、株式譲渡・合併・事業譲渡等を実施する際の資金調達を支援。公庫による融資枠が別途設けられています。 |
| 遺留分・所在不明株主 ・保証解除などの法制度対応 |
・遺留分に関する民法の特例: 後継者へ集中して承継させる際の遺留分算定除外、固定合意等 ・所在不明株主に関する会社法の特例: 株式の集約を阻む「所在不明株主」問題を簡素化する仕組み。 ・経営者保証ガイドライン: 法人・個人の財務・情報開示の要件を満たせば保証なし融資の可能性。 |
| M&A支援 | |
|---|---|
| 中小企業事業再編投資損失準備金 (据置期間あり) | M&A・事業再編を実施した場合、投資額の一部を「準備金」として損金算入できる制度。 |
| 登録免許税・不動産取得税の特例 | 事業譲渡、合併、分割を契機とする不動産、登記権利の移動時に、税率軽減措置が適用される場合があります。 |
| 中小企業投資育成株式会社による支援 | M&A・グループ化を促進する観点から、投資育成会社による出資・共同出資スキームが利用可能。 |
| 後継者人材バンク | 後継者不在の企業と、創業または事業承継を希望する人材・起業家をマッチングする仕組み。 |
| M&A支援機関登録制度 | 中小M&Aにおける仲介、FA(フィナンシャル・アドバイザー)等の行動指針を整備し、登録支援機関からの支援が補助金対象となるなど、制度的な信頼基盤を創設。 |
| 環境整備・ツール・支援体制 | ||
|---|---|---|
| 事業承継診断 | ||
| ローカルベンチマーク | ||
| 経営デザインシート | ||
| 経営者保証ガイドライン | ||
| 支援機関のネットワーク、登録制度 | ||
■参考資料
[中小企業庁]
「事業承継を知る」「事業承継を実施する」
「事業承継・M&Aに関する主な支援策」
「事業承継マニュアル」
[帝国データバンク]
「人手不足倒産の動向調査(2025年上半期)」