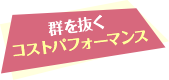Management Column女性総理誕生を機に考える企業の取るべき道

第104代内閣総理大臣に自民党の高市早苗総裁が選出され、憲政史上初の「女性総理大臣」が誕生、一般家庭出身の女性が、トップに立つという歴史的な瞬間を迎えました。長く問題視されてきた政治の世襲依存と、女性の社会進出の低さに対して大きな転換点となる出来事といえるでしょう。
しかし、日本のジェンダーギャップ指数は世界148カ国中118位(2025年)と依然として低迷しています。企業の現場では賃金差、女性管理職比率の伸び悩み、登用パイプラインの細さ、そして閉鎖的な後継選抜といった構造的課題が数字として表れています。
本コラムでは、女性総理誕生という歴史的転換点を機に、企業における具体的なジェンダーギャップ解消の取り組みにつなげるための道筋を探ります。
1.いまの日本の現状
総裁選が始まる前の2025年6月12日に発表された日本のジェンダーギャップは、世界経済フォーラムが発表するジェンダー・ギャップ指数(GGI)において、世界148カ国中118位と深刻な状況にあります。特に政治分野と経済分野における男女格差の大きさが、順位を押し下げる要因となりました。

また、企業における女性の活躍を示す指標を見ると、プライム市場上場企業の女性役員比率は18.4%、経団連会員企業でも19.0%に留まっています。政府は2030年までに30%という目標を掲げていますが、現状ではその達成には課題が残されています。
特に懸念されるのは、女性役員が一人もいない「ゼロ企業」がプライム市場でも2.4%存在することです。さらに、女性の就業状況を示す特徴的なデータとして「L字カーブ」があります。これは30代以降の女性の正規雇用比率が大きく低下する現象を指します。
この背景には、出産・育児期における仕事との両立の難しさがあります。実際、若年層の意識調査では、「性別は関係ない」と考える人が約7割いる一方で、「仕事と育児の両立に不安」を感じる人が72.2%に上っており、制度面や職場の支援体制の不足が浮き彫りとなっています。
2.女性の活躍の推進に向けた体制整備
■女性活躍推進法の情報公表
女性活躍推進法は2016年4月に施行され、「日本社会に根強いジェンダーギャップの解消と、急速に進む労働力不足への対応」を目的としており、当初は2026年3月31日までとなっていた法律の有効期限が、2036年3月31日までに延長されました。
2022年7月8日から、常時雇用する労働者が301人以上の事業主は「男女の賃金の差異」の情報公表が義務付けられ、常時雇用する労働者が101人以上300人以下の事業主は、指定された16項目から任意の1項目以上の情報公表が必要になりました。 2026年4月1日から従業員数101人以上の企業は、「男女間賃金差異」及び新たに「女性管理職比率」の情報公表が義務となります(従業員数100人以下の企業は努力義務の対象)。
対象となる企業は、施行後最初に終了する事業年度の実績を、その次の事業年度開始後おおむね3か月以内に公表する必要があります。この取り組みにより、企業の賃金格差の実態が可視化され、格差是正に向けた具体的な取り組みが促進されることに期待されています。

■上場企業における女性役員の状況
企業における女性の活躍推進は、個人の能力発揮の機会を確保するだけでなく、多様な視点を経営に取り入れることでイノベーションを促進し、日本の経済社会に活力をもたらす取り組みです。
政府は「女性活躍・男女共同参画の重点方針2023」において、東証プライム市場上場企業に対して2つの目標を設定しました。1つは「2030年までに女性役員比率30%以上」、もう1つは「2025年までに女性役員を最低1名以上選任」です。これらの目標達成に向けて、2023年10月に東京証券取引所の上場規程が改正され、企業行動規範に明記されました。
3.えるぼし認定とは
“取組”と“実績の見える化”を両輪とするのが「えるぼし認定」です。えるぼし認定は、女性活躍推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定・届出した企業のうち、女性活躍に関する取組や実績が一定の要件を満たした場合に厚生労働大臣が認定する制度です。
えるぼし認定には、1~3段階の区分があり、5つの評価項目(採用、継続就業、労働時間等の働き方、管理職比率、多様なキャリアコース)のうち、満たした項目数で段階が決まります。上位区分として、取組・実績が特に優良な企業を対象とする「プラチナえるぼし」があります。プラチナえるぼし認定企業は、一般事業主行動計画の策定・届出が免除されます。
| えるぼし認定の主なメリット | |
|---|---|
| ■認定マークの活用 | 商品・広告物・名刺・事業所掲示・自社サイト・求人票(ハローワーク表示)などに「えるぼし/プラチナえるぼし」ロゴを使用してPRできます。 |
| ■公共調達での加点 | 入札・企画競争で加点評価の対象となり、調達によっては有利に働く場合があります(配点例あり)。 |
| ■金融面の優遇 | 日本政策金融公庫の「働き方改革推進支援資金(企業活力強化貸付)」を通常より低金利で利用可能。 |

4.人材戦略にも新しい視点
一般家庭出身の女性が、日本のトップに立つという前例が、今後、企業の人材戦略にも新しい視点をもたらすのではないでしょうか。
今、企業に求められるのは、単なる"象徴"で終わらせない具体的な行動です。2026年4月からの情報公表制度の拡大を好機と捉え、賃金差・女性管理職比率のKPI化と一般事業主行動計画の実効運用、そして「えるぼし」認定の取得を軸に、採用・登用・評価・開示のPDCAを実践していく必要があります。
今こそ、従来の枠組みにとらわれない多様な人材の登用と、それを支える公平な評価・報酬体系の整備に着手すべき機会ではないのでしょうか。
■参考資料
【一般社団法人日本経済団体連合会】
「上場企業役員ジェンダー・バランスに関する経団連会員企業調査結果 2025」【厚生労働省】
「労働政策審議会労働政策基本部会 報告書(第4期) (素案)」男女共同参画局「GGI ジェンダー・ギャップ指数」
「令和7年労働施策総合推進法等一部改正法のポイント」
「えるぼし認定の概要」
「えるぼし認定、プラチナえるぼし認定」
若年層における仕事と育児の両立に関する意識調査(速報)」